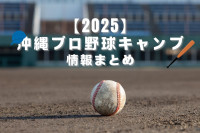【長野から沖縄へ】沖縄の文化にふれる2泊3日の旅
- 掲載日:
- 2025.04.08
長野県と沖縄県の交流連携に関する協定をきっかけにご縁をいただき、沖縄県にやって来ましたGoNAGANO(長野県公式観光サイト)ライターの佐藤です。
冬でも暖かく、透明度の高い美しい海に囲まれた沖縄は、長野県民にとってまさに理想郷。沖縄ならではの伝統文化に触れたり、海の生き物と出会ったりと、長野県では味わえないさまざまな体験を取材してきました。すベてが新鮮で感動に満ち溢れた2泊3日の旅の様子を、どうぞご覧ください!
【長野県と沖縄県の交流連携とは】
日本を代表する「海洋文化リゾートの沖縄」と「山岳高原リゾートの信州」という対極にある強みやそれぞれの魅力ある環境・資源を活かし、連携を強化することにより両県の観光産業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的としています。
【関連リンク】
INDEX
【Day1】海沿いドライブで本島中部へ。やちむんの里とブセナ海中公園
那覇空港へ降り立った時に感じる、少し蒸し暑い空気感。そして出迎えてくれた「めんそーれ」の看板。沖縄に来たことを実感し、わくわくと高揚した気持ちで、早速レンタカーの手続きへ。
今日は、那覇市内の壺屋やちむん通りに立ち寄った後、本島中部へ向かいます。一番の目的は読谷村の「やちむんの里」。沖縄の伝統的な焼き物をつくる19の工房、ギャラリー、ショップなどが集まるエリアで、那覇空港から車で1時間ほどの場所にあります。
やちむんとは、沖縄の方言で「 焼き物」のことで、ぽってりとした厚みと大らかな絵付けが特徴。もとは那覇市中心地の壺屋で「壺屋焼」として作られていましたが、戦後の人口増加で煙害が指摘されるようになり、登り窯での製作にこだわった陶工が読谷村に移り住んだことから、やちむんの里が形成されていったそう。
以前から雑誌などで見かけ、憧れていたやちむん。あのすてきな器を、いつか現地で手に取ってみたい、おみやげに買いたい!と思っていたので、今回念願叶って、とても楽しみにしていました。
まずは読谷村にある「 陶眞窯(とうしんがま)」で陶芸体験&工房見学に参加します。
①陶眞窯(陶芸体験・ 工房見学)
昔ながらの壺屋焼の伝統を守りながらも、「常に新しいものを」をポリシーに、日々作品作りに取り組んでいる陶眞窯。
器やシーサー作り、電動ろくろ、絵付けといったさまざまな陶芸体験も実施しており、今回は「うつわ作り陶芸体験」に参加。
教えてくれたのは、イギリス出身のエリさん。エリさんはなんと、ロンドンの大学でやちむんのことを知り、やちむんの温かみや色使いに惹かれ、陶眞窯で働きながら陶芸と日本語を勉強中とのこと。やちむんは国境を超えて人を魅了するのだと、なんだか嬉しくなります。
平皿やカップなど、作りたい器を選びます。私は今回カップにしました。
柔らかくてしっとりした赤土をよくこねて麺棒でのばし、型の形にカットしていきます。それを型に巻き付けて成形したら、沖縄の伝統的な唐草模様、ミンサー模様などのハンコ、サンゴなどで模様をつけていきます。これで一気に沖縄らしい器に! 黒か白の釉薬を選び、あとは焼き上がりを待って、自宅には約1ヶ月後に届くとのこと。どんなカップに仕上がるか、楽しみです。
体験後、工房を見学させてもらいました。20以上の工程があり、分業制でそれぞれが自分の仕事に真摯に取り組んでいます。ロクロでさまざまな器の形を作る人、絵付けをする人、化粧掛けをする人、釉薬をかける人など。そして週に2回の窯焼きを経て、ようやく完成します。
驚いたのが、土作りや釉薬作り。赤土は厳選した沖縄の土をブレンドしており、釉薬は沖縄でとれる籾殻・珊瑚や貝殻を焼いた消石灰・白土をオリジナルで配合しているそう。そしてそこに描かれるのは、赤・緑・青・黄など明るい色に、沖縄らしい唐草やデイゴ、魚紋などのモチーフ。やちむんは、沖縄の自然そのものが詰まった、そしてそこに生きる人々が生み出す唯一無二のものづくりなのだと、現地に来たからこそのストーリーを知り、深く心に残りました。
併設のショップには、見学した器の完成品がずらり。手に取れば、素朴ながらも力強く、やちむん特有の温かみを感じます。普段使いしやすいものばかりで、あれもこれも欲しくなりますが、悩みに悩み抜いて数枚購入。
そして沖縄ならではの器も発見。酒壺です。地元の人はここに泡盛を入れて、結婚や退職などのお祝いに贈る習慣があるそう。初めて見たので、びっくり!また「カラカラ」という泡盛を飲むための酒器もありました。酒壺から掬った泡盛をカラカラに入れて、そこから泡盛を飲むそうで、日本酒でいう徳利です。
自分の知らなかった、沖縄ならではの文化に触れ、また一つ自分の視野が広がっていくのを感じました。
②やちむんの里・Clay Coffee & Gallery
やちむんの里を歩くと、シンボルである沖縄らしい赤瓦の登り窯を中心に、工房や売店があちこちに点在しています。緑溢れる環境で、制作途中の器がずらりと天日干しされている光景や、あちこちに佇むシーサーなどを見ているだけで、幸せを感じます。こののんびりとした空気感も作品の大らかさに影響を与えているようです。
「北窯 松田共司工房」の親方がプロデュースするギャラリー兼カフェ「Clay Coffee & Gallery」では、親方の作品を展示・販売するほか、その器でランチやケーキ、コーヒーなどがいただけます。
いくつかあるランチメニューの中で、沖縄といえばのタコライスをチョイス。ごはんの上には、スパイスで濃いめに味付けしたひき肉(タコミート)とレタスがどっさり。 黒い器に緑や赤が映えます。伝統的かつモダンでおしゃれな空間の中、この地で生まれた器で料理を味わう。その喜びを噛み締めながら、最後までおいしくいただきました。
③ブセナ海中公園
やちむんの里を満喫したら、やはり沖縄といえばのきれいな海を眺めたいと思い、車で北上すること約40分。「ブセナ海中公園」へやってきました。
透き通ったエメラルドグリーンに、きらきら反射する波間。天国とはまさにこのことかと思うほど美しく、いつまでも眺めていられます。長野県民は強烈に海への憧れがあるため、ふだん見られない海の景色に、より一層心の底から癒されます。
冬のオフシーズンなので人も多くはなく、ゆったりと海岸を歩きながら海中展望塔へ。螺旋階段を降りていくと、水深約3メートルの海中の世界へ辿り着き、24面の窓から珊瑚礁や色鮮やかな魚たちを間近に観察できます。
上から眺めていた海が、潜るとこんなにたくさんの魚や海藻、珊瑚礁などの生き物で溢れる、豊かな世界が広がっていたとは。目の前をタマン、カクレクマノミ、チョウチョウウオなどがゆらゆらと泳いでいきます。海のすばらしさをしみじみと味わいながら、これからもこの世界が守られますようにと切に願うのでした。
泳げなくても、雨でも、冬でも、服を着たまま快適に海の世界を覗くことができる、沖縄唯一のスポット。天候条件が良ければ船底がガラス面になったグラスボートに乗って沖合の海中散策ができる体験もあります。
【Day2】琉球王国文化に触れる首里さんぽ。夜は国際通りへ
1879年に沖縄県になるまで、約450年間にわたって存在していた国家・琉球王国。中国や日本、東南アジアとの交易でさまざまな文化を取り入れながら、独自の琉球文化を形成していきました。
その王国の政治・外交・文化の中心として栄華を誇ったのが首里城で、首里城下町を歩くと、琉球王国時代の名残を感じさせる場所が多数あります。やちむんに続いて、せっかく沖縄に来たならと、2日目は琉球王国から受け継がれている伝統文化に触れてきました。
④首里城公園
首里城といえばの赤が目印の「守礼門」をくぐり、ゆるやかな坂道を登りながら城壁や複数の門を通り抜けていきます。随所に中国と日本の影響を受けているという独特の建造物に、異国情緒を感じてわくわく。ハイビスカスなどの長野では見かけないカラフルな花々もきれいに手入れされ、冬でも花が咲いていることにも驚きます。広福門の手前あたりはビュースポットとなっており、市街地や遠くに東シナ海も望めました。
2019年の火災で正殿を含む9つの施設は再建中。「見せる復興」をテーマに、見学エリアから復元工事の様子も見られるとのこと。今回は立ち寄りませんでしたが、また次回来るときにはきっと完成しているであろう正殿が見られることを、心待ちにしたいと思います。
⑤瑞泉酒造
首里城から歩くこと約10分。沖縄といえばの泡盛を造る酒造場です。
東南アジアがルーツとされ、約600年前に造られるようになったという泡盛も、じつは琉球王国と深い関わりがあるのです。今では県内各地で造られている泡盛ですが、当時は王朝のお膝元である首里三箇(赤田・崎山・鳥掘の3カ所の村)にだけ“焼酎職”という職人を住まわせ、王府の監督下で造らせていました。そこで造られた泡盛は交易品や江戸への献上品、来客への振る舞いとして重宝されたのだそう。泡盛は沖縄独自の“黒麹菌”が使われていることも特徴です。
そんな伝統ある首里三箇の崎山エリアで、焼酎職を始祖に持ち、1887年に創業した「瑞泉酒造」。泡盛の製造工程や歴史などを、展示資料やビデオを通じて学ぶこともできます。
瑞泉酒造は、ゆっくり時間をかけて3年以上熟成させた泡盛の古酒にこだわりを持ち、長いと数十年も経過した古酒もあります。古酒に若い酒を注ぎ足す「仕次」という方法で、年月を重ねるほどにまろやかで芳醇な味わいになるといい、蔵内には年代物の大きな甕がずらりと並んでいました。
何種類か試飲してみると、熟成期間などの違いで味の甘みや濃さなど、まったく異なります。水で割ったりロックで飲んだりと、その味わいの変化も楽しみつつ、すっかりいい気分。
泡盛は沖縄のお酒、という認識はありましたが、その歴史や製造方法を知り、やちむんの里でも泡盛の器を見たりすると、沖縄の人々の生活にいかに深く結びついているのかと分かります。
⑥首里染織館Suikara
泡盛で気分が良くなったところで、続いて向かったのは「首里染織館Suikara」。
琉球王国のお膝元で磨かれてきた「首里織」という織物と、「琉球びんがた」という染め物の伝統技術を学び、つなぐ場所です。琉球王国時代、海外からもたらされた技法を発展させて作られていた伝統工芸品で、王族・貴族も愛用していました。
1階は作品のギャラリーやショップ、2階は琉球びんがたの作業室、3階は首里織の作業室。
体験プログラムも実施されており、オリジナル柄のびんがたをトートバッグに染める体験や、絹糸の花織を織る体験ができます。
南国らしい色使い、沖縄の自然を感じさせる緻密な意匠など、どれもこの土地じゃないと生まれてこない色とデザイン。見ているだけで元気が湧いてきます。ポーチやクッションカバー、ポストカードなど日常使いできるアイテムも多いので、沖縄みやげにぴったりです。
⑦角萬漆器
14・15世紀頃に中国から伝わり、琉球王国時代には祭祀や儀礼などの場、外交の献上品などで用いられてきたという琉球漆器。沖縄の県花であるデイゴやシタマキなどの木材を使用し、螺鈿や堆錦などの加飾技法が盛り込まれ、華美な印象を受けます。長野県にも木曽漆器という漆器がありますが、日常の生活に根差した素朴な風合いなので、同じ漆器でもその特徴の違いに驚きます。
そんな琉球漆器の伝統を受け継ぐ「角萬漆器」は、伝統を尊重し守りつつも、現代に合う漆器のさまざまな可能性を提示しています。
まずお店の空間からモダン。漆器や伝統工芸というイメージを覆すとてもおしゃれでシックな内装で、赤や黒の漆器一つひとつの美しさが際立ちます。
食器類のほか、新たに挑戦し始めたという漆器のアクセサリーも。どれもセンスが良く、うっとり。まずはこうしたアイテムから、日常に漆を取り入れてみるのもいいかもしれません。
さらにカフェも併設されており、コーヒーやアイスクリームなどのスイーツが角萬漆器の器でいただけます。食は器と密接に関わっており、食を通じて漆器の良さも体感してもらおうと始められたそう。
歴史ある琉球漆器がより身近に感じられる、すてきなお店でした。
沖縄の気候風土、そして琉球王国が取り入れたさまざまな国の文化や技術。それらが合わさって独自に進化を遂げ、現代に伝わる沖縄ならではの伝統工芸や文化が出来上がっていったということが、肌で感じられた首里さんぽでした。
首里城を起点に、どこも徒歩で巡れる距離だったので、ぜひ実際に商品を手にとりながら、その素晴らしさを体感してほしいです。そしてこうしたものづくりが一つでも生活に加われば、暮らしはより豊かになるのだと思いました。
⑧夜は国際通りでジャズバー
沖縄観光の定番であり、一大繁華街である国際通り。どこからともなく三味線の音が聞こえ、夜でも人通りは多く、賑やかな声が飛び交います。昼間の落ち着いた首里の雰囲気から一変し、こうした活気も沖縄の魅力。
国際通りからあちこちにのびるアーケードの商店街をぶらぶら歩くと、ディープでレトロな酒場や食堂も見かけました。地元民御用達なのだろうか、この地に来ないと見られない、そんな光景にもそそられます。
市民の台所でもある「那覇市第一牧志公設市場」は、精肉店や鮮魚店がひしめき、2階には飲食店も。沖縄県外では見たことのない見た目の魚や貝の姿に、思わず驚愕。その場で買って食べることもできるので、どんな味がするのだろうと気になりながらも、勇気が出ず、また来た時にリベンジを誓うのでした。
まるで冒険気分で街歩きを楽しんだら、ちょっとシフトチェンジして、ジャズバーへ。
じつは国際通りには、毎晩のように生演奏でジャズが聴けるジャズバーが複数あるのです。沖縄のジャズ文化は戦後の米軍統治下において発展したと言い、今回は1980年に創業したという老舗の「KAM’S HOUSE」へお邪魔しました。
この日はピアノ、ベース、ギター、ドラム、トランペットの豪華セッション。すばらしい演奏に浸りながら、お酒が進みます。なんて大人で上質な時間なのでしょう。CDなどの音源で聴くのとはまったく異なる、生演奏の良さをしみじみと味わいました。沖縄でこんなすてきな夜を過ごせるなんて。余韻を引きずりながら、お店を後にしました。
【番外編】沖縄で食べた絶品ご当地グルメ
沖縄に来たら食べたいものがたくさん。沖縄そばも、ラフテーも、ゴーヤーチャンプルーも。そんな欲張りな願いを叶えつつ、沖縄観光コンベンションビューローのスタッフさんに教えてもらったおすすめ店を巡りました。
⑨沖縄そばの店 しむじょう
首里城から車で約15分。国の登録有形文化財に登録されている古民家で、おいしい沖縄そばが食べられると評判のお店。古き良き沖縄の風情を感じさせ、ゆったりとした空気が流れています。
「三枚肉そば」のセットメニューを注文。三枚肉そば、ジューシー(炊き込みごはん)、もずく酢、しょうが、ジーマーミ豆腐などがセットになっています。コシのある麺と分厚くてほろほろと柔らかい三枚肉が、深いコクのあるスープと絡み合い、たまりません…!沖縄そばと一緒に出ることが多いというジューシーも初めて食べましたが、具沢山で風味豊か。ボリュームも満点で、心もおなかも満たされました。
⑩琉球料理ぬちがふぅ 命果報
国際通り近くの「壺屋やちむん通り」にある琉球料理店。数々のメニューがある中、沖縄定番の郷土料理が一つの御膳になった、「ぬちがふう御膳」をいただきます。
食べたかったラフテーも、ゴーヤーチャンプルーも、人参しりしりなども、一つ一つやちむんの器に丁寧に盛り付けられており、見た目から心が華やぎます。天ぷらはもずくやあおさといった、沖縄ならではの食材もあり、長野県には無いもので嬉しい!どれもおいしく、滋養があり、体に染み渡るようでした。国の重要文化財(新垣家住宅 ・東ヌ窯)を眺めながら、落ち着いた古民家で沖縄料理をいただくという、空間を含めて沖縄を堪能できる名店です。
⑪味噌めしや まるたま
私が知らなかった沖縄県民のソウルフードがあると聞き、県庁や市役所近くにある「味噌めしや まるたま」へやって来ました。聞いたところ、沖縄の食堂では、どんぶりによそられた具沢山の味噌汁をメインのおかずにしてご飯を食べる、“味噌汁定食”というものが定番であるそう。
琉球王国御用達だったという首里の老舗味噌蔵「玉那覇味噌醤油」の無添加・天然醸造で作られる味噌を使った料理を提供しているこのお店で、さっそく「具だくさん味噌汁」を注文しました。
噂どおり、こちらの味噌汁もたっぷりの豚肉、豆腐、小松菜などの具材と、そして卵がどんぶりに入っており、具沢山! それをおかずに、ごはんをかきこみます。味噌汁は小さなお椀でしか飲んだことがありませんでしたが、腹持ちもよく、濃厚な味噌がご飯にも合います。いろいろな具材が入るので栄養もたっぷり。沖縄県民の仲間入りできたような気分になれて、発見と嬉しい体験でした。
【Day3】飛行機までの空き時間。空港近くの海や水族館へ
帰るのが名残惜しいほど、すべてが楽しく充実していた沖縄での時間も、残りわずか。
帰りの飛行機までの隙間時間で、空港近くで楽しめるスポットへ行ってきました。
⑫波の上ビーチ
那覇市唯一の海水浴場である「波の上ビーチ」。周辺はバーベキュー施設、公園、ダイビングスポットなどもあり、空港から車で15分ほどで来られるので、気軽に海を楽しむことができます。
波の上ビーチの脇に鎮座する大きな岩の崖の上へ歩いていくと、波上宮という神社が。琉球王国からも特別な神社として扱われてきた、歴史ある神社なのだそう。
狛犬に代わってシーサーがいたり、赤瓦の社殿などに沖縄らしさを感じたりしながら 、静かに旅の無事の感謝を伝えました。
⑬DMMかりゆし水族館
つづいて、那覇空港までは車で約20分の場所に位置する「DMMかりゆし水族館」へ。大型ショッピングセンター「イーアス沖縄豊崎」の中にあり、アクセス抜群です。
最新の映像表現と空間演出を駆使して、海の上を歩いているようなエリアがあったり、現実の時間帯に合わせて変化する沖縄の海を再現したような場所があったりと、優雅に泳ぐ海の生き物たちを眺めながら、幻想的な空間に癒されます。ペンギンや海水魚などへの餌やりなど、生き物と触れ合える体験もありました。
最後まで余すことなく沖縄の旅を満喫。沖縄の豊かな自然や歴史がもたらした、さまざまな伝統文化、色鮮やかな美しい景色、おいしいグルメなど、沖縄の魅力をたっぷり五感で味わうことができました。冬ならではの穏やかな雰囲気や、気候条件の良さも、長野県民にとって過ごしやすく、天国のようでした。
次回はあそこへ行こう、ここへ行きたい、という候補地もたくさん増え、すっかりファンになったので、このご縁を機に、また何度でも訪れたいと思います。